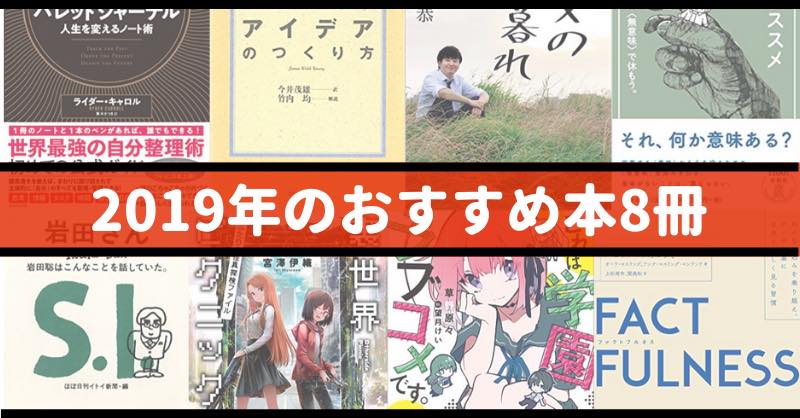
2019年は、あまり本が読めなかった。
でも同時に、読んだ冊数が少なかった割には、その1冊1冊が濃密に感じられた1年でした。自分としては珍しく、短いスパンで複数の本を再読するほど。つまり「思わず読み返したくなる」と感じるくらい、2019年に読んだ本は、自分にとって強く印象に残るものだったわけです。
本記事では、そんな8冊の本をご紹介。
当初は15冊ほど挙げてまとめるつもりだったのですが、どうせなら「本当におすすめしたい本」に絞ろうかと考え直しまして。もちろん好みはあるでしょうが、個人的に「これは周囲の人にも勧めたい!」と強く感じた書籍に限ってまとめています。ちなみに、2019年の新刊はうち5冊です。
- 『岩田さん』ほぼ日刊イトイ新聞
- 『ナナメの夕暮れ』若林正恭
- 『無意味のススメ』川崎昌平
- 『裏世界ピクニック』宮澤伊織
- 『これは学園ラブコメです。』草野原々
- 『ファクトフルネス』ハンス・ロスリングほか
- 『バレットジャーナル』ライダー・キャロル
- 『アイデアのつくり方』ジェームス・W・ヤング
- 過去の年間おすすめ本まとめ
『岩田さん』ほぼ日刊イトイ新聞
任天堂の元社長・岩田聡さんの言葉をまとめた本。
「大企業の社長の言葉をまとめた本」と聞くと堅苦しいビジネス書がイメージされるけれど、本書の読後感はまったくの別物。お偉いさんでも何でもない「岩田さん」という一個人が、その経験や考え方を淡々と語っているような、そんな光景が脳裏に浮かんできた。
それこそ、ニンテンドーダイレクトで「直接!」話しかけていたように。
振り返ってみれば、今年読んだ中でも特に強く惹かれたのがこの本だった。理由はいくつか考えられる。でも何と言っても、この1冊には多くの人の思いが込められており、読むことでその “思い” の強さを実感できるから。だからこそ、自分にとっても特別な1冊になったのだと思っています。
収録されている岩田聡さんの言葉のみならず、インタビューに答えている宮本茂さんと糸井重里さん、そして編集を担当した永田泰大さんたちも含めて、多くの人の強い思いが、この1冊に込められている。「岩田さん」という個人について語る言葉は各々に違っていても、その内容はどこか一貫していて、共通してあたたかな気持ちを感じられる。
ただ単に「岩田さんの言葉から気づきを得られるから読む」のではなく、本書に携わっている人たちの思いにもふれたいから、繰り返し読んでいる──。きっと、そういうことなんじゃないかしら。それゆえに、何度も何度も手に取っている、手に取ってしまっている1冊。それがこの、『岩田さん』という本です。
やさしくて、やわらかくて、楽しそうで……でも同時に、情熱にもあふれていて。あったかいけれど、アツい読み物。遠い存在に感じていた「岩田さん」の人柄をこうして垣間見、身近に感じることができたのは、いちユーザーとして本当にありがたく思います。今年もお世話になります。
やさしくてあったかい、1人のゲーマーが紡いだ言葉の数々『岩田さん』
『ナナメの夕暮れ』若林正恭
オードリー若林さんのエッセイ集。
正直に言うと、芸人に詳しくない自分は筆者さんのこともほとんど知らずに読み始めたのですが……むっっっちゃくちゃ共感できて、おもしろく読めました。
純粋に驚いたのが、「日常で感じる違和感や漠然とした『生きづらさ』を、ここまで見事に言語化できる人がいるのか!」ということ。必ずしも答えがある話ばかりではないものの、自身が普段から抱えているモヤモヤに対するちょっとした気づきを与えてくれる。読んでいて胸のすくような感覚があった。
電車での移動中に少しずつ読み進めていたのだけれど、最後のほうは「途中で栞を挟むのがもったいねえ!」と感じるほど夢中になり、まっすぐ家に帰らず、深夜の最寄り駅のホームで読みふけってしまった。本書もまた、2019年読んだ本としては強く印象に残っている1冊です。ご結婚おめでとうございます!
〝好きなことがある〟ということは、それだけで朝起きる理由になる。
〝好き〟という感情は〝肯定〟だ。
つまり、好きなことがあるということは〝世界を肯定している〟ことになる。
そして、それは〝世界が好き〟ということにもなるという三段論法が成立する。
(若林正恭『ナナメの夕暮れ』Kindle版 位置No.1403より)
『無意味のススメ』川崎昌平
僕らの日常は数々の「意味」に囲まれている。看板や地図といった「意味」がなければ目的地にはたどり着けないし、ルールやマナーは人間関係を円滑にし、本やテレビは未知の知識と「意味」を教えてくれる。
でも同時に、過剰すぎる「意味」はしばしば僕らの心を疲弊させる。
そんな「意味」に対抗する手段として、本書は「無意味」の価値を明らかにしていく。曰く、「意味と意味のあいだに生まれる『無意味』には、慌ただしい日々における余白として、人の心を休める効果がある」と。
ルーチンワークを楽だと感じることもあるけれど、同じことばかり続けていても、精神的に「消耗している」と感じることがある。そんなとき、代わり映えのない生活に「無意味」を混入させてやると、何でもない景色や行動が色づいて感じられる。その瞬間、「無意味」は「意味」へと昇華され、また新たな「無意味」が顔を覗かせる。
情報や意味から逃れ、リラックスしたいときに読みたい。僕自身、もう何度か繰り返し読んでいる1冊です。
読書感想『無意味のススメ〜〈意味〉に疲れたら、〈無意味〉で休もう。』
『裏世界ピクニック』宮澤伊織
「エモい風景は、それだけで百合」「百合が俺を人間にしてくれた」*1「観測できない百合を書きたい」*2などのパワーワードをインタビュー記事で繰り出しまくっていた、作家・宮澤伊織さん。「ここまで圧のある言葉を聞かされたら、そりゃあ著作を読まないわけにはいかないでしょう!」ということで、読みました。
──百合、でした。
圧倒的な百合。いや、そんな濃密に百合百合しているわけではなく、作中のエッセンスのひとつに過ぎないものの、すばらしく百合。明らかに自分好みの、関係性にフォーカスした百合。あっ、でも、あのその、べっ、別に僕は百合作品はそんな読んでませんし? 詳しくはわかりませんけど? でも好きです!!
百合要素の解説は専門家さんにお願いするとして、おそらくは「初心者向けSF小説」としてもおすすめできそうなシリーズ。「街中に異世界への入り口があり、その先で次々に怪異と出逢う」という物語展開は珍しくないものの、その舞台設定が緻密かつ独特で、またキャラクターも魅力的な作品となっている。
というのも、本作における〈裏世界〉で出逢う怪異たちは、インターネットではおなじみのものばかり。「くねくね」「八尺様」「きさらぎ駅」といったネットロアを下地に、本作独自の解釈も加えつつ語られる怪異。どれもこれも興味深く、恐ろしく、元ネタ以上に実在性を伴っているように感じられた。
まだ1巻しか読めていないものの、これだけ楽しめて、しかも百合とくりゃあ、続刊も読むしかあるまいて。さらに、コミカライズを担当しているのが自分の大好きな水野英多先生と聞いたら、そりゃあポチらざるをえないってもんでしょう。『スパイラル』はいいぞ。
『これは学園ラブコメです。』草野原々
表紙を見れば、望月けいさんが描いたかわいらしい女の子。
タイトルを読めば、「これは学園ラブコメです。」の文字。
……そうか、なるほど!
これは学園ラブコメなのか!!
──なーんて、素直に受け取ってはいけない。こんなにも自己主張強く「ラ ブ コ メ で す」なんて断言している作品が、本当に王道ラブコメのはずがない。「こじらせたオタクほど穿った目で作品を見る」という人もいるけれど、これは疑ってかかるべき作品だ。だって、作者が作者なのだから。
本作は、『最後にして最初のアイドル』などで注目を集めた作家・草野原々さんによる、学園ラブコメである。……そう、ラブコメである。決して間違ってはいない。複数のヒロインが登場し、主人公をめぐって、しっちゃかめっちゃかする。幼なじみも転校生も後輩もいるし、ラッキースケベもある。やったぜ。
ところがどっこい。事はそう単純ではない。いや、割と単純と言えば単純ではあるのだけれど、うまく説明するのが難しい。Amazonのトップレビューから一言だけお借りすると、「メタフィクションをメタフィクションしている」という指摘が、この作品の本質と言えるかもしれない。
「ラブコメ」とはいったい何なのか。ラブコメをラブコメたらしめているのはどのような要素なのか。いや、ラブコメに限らず、物語における「ジャンル」とはいかにして定義されるのか。最後には小説世界における「お約束」とバトルを繰り広げることになる主人公は、はたしてどこへ向かうのか──。
あまりにも濃厚でハイテンションで胃もたれしそうになるけれど、最終的には「物語とはなんぞや」と思いを馳せずにはいられない作品。「お話」と「お約束」の妙を楽しみつつ、世界の意思に都合よく動かされるキャラクターたちを憂いつつ、それでも僕は、ラブコメの主人公を羨ましいと思うのです。
『ファクトフルネス』ハンス・ロスリングほか
ビル・ゲイツ氏曰く「世界を正しく見るために欠かせない1冊」。
──いや、さすがに言いすぎでしょう……と思いきや、冒頭の13問のクイズに答える頃には、そんな印象は吹き飛んでいた。そこで明らかになるのは、「世界は良くなっている」という紛れもない事実。本書では、その事実を歪めてしまう人間の「本能」について紐解いていく。
「ファクトフルネス」が示すのは、データの大切さは言うまでもなく、視野狭窄を回避する複眼的なモノの見方や、思い込みを排除するための考え方など。約20年間で大きく様変わりした世界の姿を再確認しながら、今後は誤った真実に踊らされないようにするための「世界の見方」を知ることができる。
正しい世界の見方って?日常生活でも使える複眼思考『ファクトフルネス』
『バレットジャーナル』ライダー・キャロル
世界中で注目を浴びているノート術、バレットジャーナル。その考案者が著した公式ガイドブック、それがこの本だ。
てっきりクリエイティブな人向けのノート術なのかと思っていたら、その方法は驚くほどにシンプル。「箇条書き」を中心に据えたメモを積み重ねることで日々の「自分」の姿を可視化し、客観視し、生活の改善を目指す。それがこの、バレットジャーナルなのだそう。
筆者自身の哲学や具体的な事例も数多く登場するため、説得力も強く、共感しながら読み進められる。自己啓発書としての要素が強い後半を不要と考える人もいるようだけれど、個人的には、後半で説明される筆者の哲学が、前半のハウツーの有用性を高めてくれているように感じた。
単なるハウツー本にとどまらない、本当に「人生が変わる」かもと思える1冊。実際、僕の人生は少なからず変わった……と思う。ただ、まだうまく有効活用できていない気もするので、もう1年はあれこれと試してみようかな。
『バレットジャーナル』のメリットは?公式入門書が紐解く最強のノート術の真髄
『アイデアのつくり方』ジェームス・W・ヤング
わずか52ページ、60分ほどで知的発想法の本質を学べる、80年以上にもわたって世界中で読まれ続けているロングセラー本。ビジネスパーソンのみならず、クリエイター界隈でもしばしば「おすすめ本」として挙げられているのが気になり、一気に読了。
「どこかで聞いたことがある」と感じる人も多いかもしれない。けれど、「当たり前」の考え方だからこそ折に触れて再確認する必要もあるだろうし、ありふれたことほど、実践し続けるのは難しい。数多く出版されているアイデア本の中でも発想法の「本質」を凝縮し、明快にまとめ上げた1冊です。
アイデアを生み出す5段階とは?60分で読めるロングセラー本『アイデアのつくり方』
過去の年間おすすめ本まとめ
- 2019年:この記事
- 2018年:本当におすすめしたい17冊まとめ
- 2017年:本当におすすめしたい20冊まとめ
- 2016年:本当におすすめしたい19冊まとめ
- 2015年:本当におすすめしたい30冊まとめ
- 2014年:本当におすすめしたい21冊まとめ
- 2013年:本当におすすめしたい15冊まとめ
- 全体:おすすめ本154冊まとめ〜読む本に困ったときの参考に







